最終更新日: 2025年4月18日
プラトンが何かを説明するときによく用いる「比喩」は、別に哲学に興味がない人でも、そのストーリーに夢中にさせてくれます。
そして、そのストーリーにのめりこんでいるうちに、気づけば大切なことを学ばせてくれる・・・プラトンの比喩にはそんな不思議な魅力があります。
今回紹介する「洞窟の比喩」は、そうした中でも、プラトンの真髄や魅力をもっともよく表している比喩だと個人的に思っています。
代表作「国家論」であらわされたこの比喩で、プラトンは、人間がどのようなプロセスで善の輝きに目覚め、そして、本当の幸福に到達するのかを、非常にシンプルかつ明瞭に描きました。
洞窟の比喩のストーリー
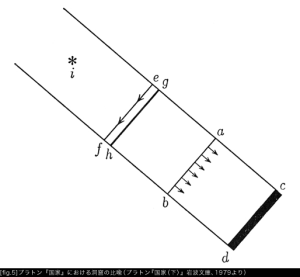
地下にある洞窟の中に、囚人が住んでいます。
彼らは子供の時から手足も首も縛りつけられているため、ずっと目の前にある壁(cd)だけを見て生活しています(ab)。
また、彼らの後上方はるかのところに、火がともっていますが(i)、囚人たちは背後を向くことができないので、見ることができません。
そして、囚人と火の間の通路(ef)には、低い衝立(gh)が置かれています。
その上から操り人形を出して見せると、ちょうど火に照らされた操り人形の影や、そこを通り過ぎる物などが、囚人の見ている壁(cd)に投影されます。
この過ぎ行く影のみをずっと見ながら生活しているうちに、囚人は、影こそが真実であると認めるようになります。
すると、その影の動きを鋭く観察し、次の動きを推測するようなことをやり始め、それを誰よりも上手くできた囚人には名誉や賞賛が与えられるようになります。
太陽を仰ぎ見る
しかし、ある時、囚人のひとりが縄をほどかれ、背後にある火の光を仰ぎ見るように強制されます。
これまで影ばかり見ていたその囚人は、光に目がくらんでよく見えないばかりか、苦痛を覚えます。
そのため、やはり向きかえり、自分にとってよく見えやすい影をまた見ようとします。
さて、ここで、ある誰かがその囚人を無理やり洞窟の急な荒い道を引っ張って行って、火のさらに向こうにある出口、太陽のある世界に連れていきます。
すると、当然ながら囚人はまぶしさのあまり、最初のうちは何も見ることができなくなります。
そこで、囚人はまずは水面にうつる太陽の光を見て、次に夜の星を見るというように、目を明るさに慣れさせていき、最終的には、太陽そのものを見ることに成功します。
さて、囚人は、その太陽の光を知ってから、今まで自らが見ていたものがただの影であったことや、またその地下の影ですらも、太陽がなんらかの仕方で原因となって発生していたことを悟ります。
囚人はこの体験を非常に幸福に思うと同時に、洞窟にいる他の囚人たちに憐れみの情がわいてきます。
再び洞窟へ戻る
その囚人は、自分の体験を伝えるべく、また洞窟に戻り、自らの体験を伝えようと試みます。
しかし、光に目が慣れてしまったために、今度は影をうまくみることができないという事態が発生します(時間が経って目が慣れさえすれば、影すらもよりよくとらえることができますが)。
そのため、他の囚人は、「あいつは、上で光を見たせいで、すっかり目をだめにしてしまった」とその囚人を笑いものにします。
そして、囚人たちは、もし仮に自分達を無理やり上に連れて行こうとする者がいるならば、殺してでも阻止しようとするようになります。
光を見た囚人にしてみれば、そのような洞窟にいるくらいなら、太陽のもとで光を受けながら生活したほうがよほど幸せにみえます。
しかし、それでも彼は、洞窟に入り、また彼らと同じような影を見る生活を送りながら、それらの囚人を真実の幸福に導くために行動しなければならないのです―
以上が洞窟の比喩の概要です。
洞窟の比喩が表していること

洞窟の比喩の意味をプラトンの思想をベースに解釈するならば、以下のようになると考えられます。
・太陽:善そのもの、イデア。
・影(cd):火から投影された動物的な快楽、例えば、物質欲、金銭欲、権力欲など。
・影を見る囚人(ab):動物的な快楽(=影)こそが真実であり、価値があるものとして追いかけ、その挙動に一喜一憂する人々。
・衝立(ef)で人形を操る者:囚人の裏で動物的快楽という影を作り出し、その追求を本人たちが気付かないように扇動している人々。
・背後にある火(i):善に近い光ですが、この光は、さらに上方に控える太陽とは似て非なる性質を持つものでしょう。なぜなら、火は、太陽とは違い、一定の範囲しか照らすことができないものだからです。
この火について特に解説はありませんが、恐らく、自分に利益がある限りは、相手のためになることをする、そんな打算的な偽善を指しているのかもしれません。
洞窟の中の状況は、この一見善に近いものの、範囲が限られた小さな善の光にのせて、ある人々は囚人の享楽的快楽をあおり、囚人はその快楽の影こそが真実だとして追いかけ生活をしている、という状況でしょう。
洞窟の比喩と真のリーダー

次に、この状況から囚人を太陽のあるところまで無理やり連れて行くのが、ある種の「リーダー」です。
そのリーダーは、すでに善そのものの光を知っているからこそ、囚人を外に連れ出すことができるし、ぜひともその光を囚人に知ってほしいと望んでいるのです。
まず、リーダーは囚人を連れ出すにあたって、その光の素晴らしさや、今多くの人々が追いかけているものが影でしかないことなどを詳しく説明し、説得を試みるでしょう。
そこで多くの人々の失笑を買うものの、多少なりとも理解を示した一部の囚人は、そのリーダーについていき、体と魂を影から向け変え、善そのものに近づいてみようとします。
善なるリーダーの行動
善そのものに近づくには、従者と馬の比喩で述べられたような、創造行為や、あらゆる種類の徳の実践を行います。
しかし、快楽に浸ることが習慣であった囚人は、この善に近づくことに幾度となく挫折し、もとの生活に戻ろうとしてしまうでしょう(魂の欲望的部分)。
しかし、それでもリーダーは、囚人が慣れるまで、様々な援助をしながら、辛抱強く善そのものの方へ向かせようとし、囚人も自らを奮い立たせる努力をします(魂の気概の部分)。
そうして、苦労しつつも、善に近づいていくうちに、囚人もだんだんとその光をもっと体験したいと思うようになり、そのためにますます節制をすすめ、より光を浴びることができるように努力します(魂の理知的部分)。
そして、苦労の果てに、囚人がついに善そのものを観るに至ると、恐らくマズローのいう「至高体験」のような、感動の瞬間につつまれるのかもしれません。
そこまでおおげさなものでなくとも、これまでの肉体的快楽より、はるかに素晴らしい体験をすることができるはずでしょう。
その後、そのような体験をした囚人は、この素晴らしさをさらに別の囚人に教えるために、今度は自らがリーダーとして、再び他の囚人の中に入っていき、先代のリーダーがしてくれたことを行っていきます。
プラトンは、そんなリーダーが哲学によって誕生し、真実に善の輝く世界が実現することを願って、この比喩を書いたのかもしれません。
↓↓↓
本当の善に到達するためには、圧倒的に「瞑想」がオススメ!その理由をご紹介します。







コメントを書く